実は長い歴史を持つ「医療ビデオゲームの世界」をご存じですか
プレイすることで、医療従事者の苦労を知ることができるかも!
新型コロナウイルスは医療ゲームの創始者の命すらも奪い去った……
未知のウイルスがもたらす脅威は、人間の立場や知名度を問わず、誰にでも平等に降りかかる。映画スターだろうと、コメディアンだろうと、 一介の労働者だろうと、ウイルスは分け隔てなく、誰もが平等に感染する可能性がある。そんな最中の2020年4月11日、イギリスでジョン・コンウェイ氏(82歳)が新型コロナウイルス(COVID-19)による感染症で亡くなった。ぼくはそのことに大変なショックを受けた。
……ところで、ジョン・コンウェイって誰?世間ではそうクビをひねる人が大半だろう。それは無理もない。
ジョン・ホートン・コンウェイ(John Horton Conway)は、イギリスの天才数学者だ。その分野でいくつもの輝かしい受賞歴を誇る存在だが、 彼の名前が一般に知られるようになったのは、他ならぬ「コンピュータゲーム」でのことだった。
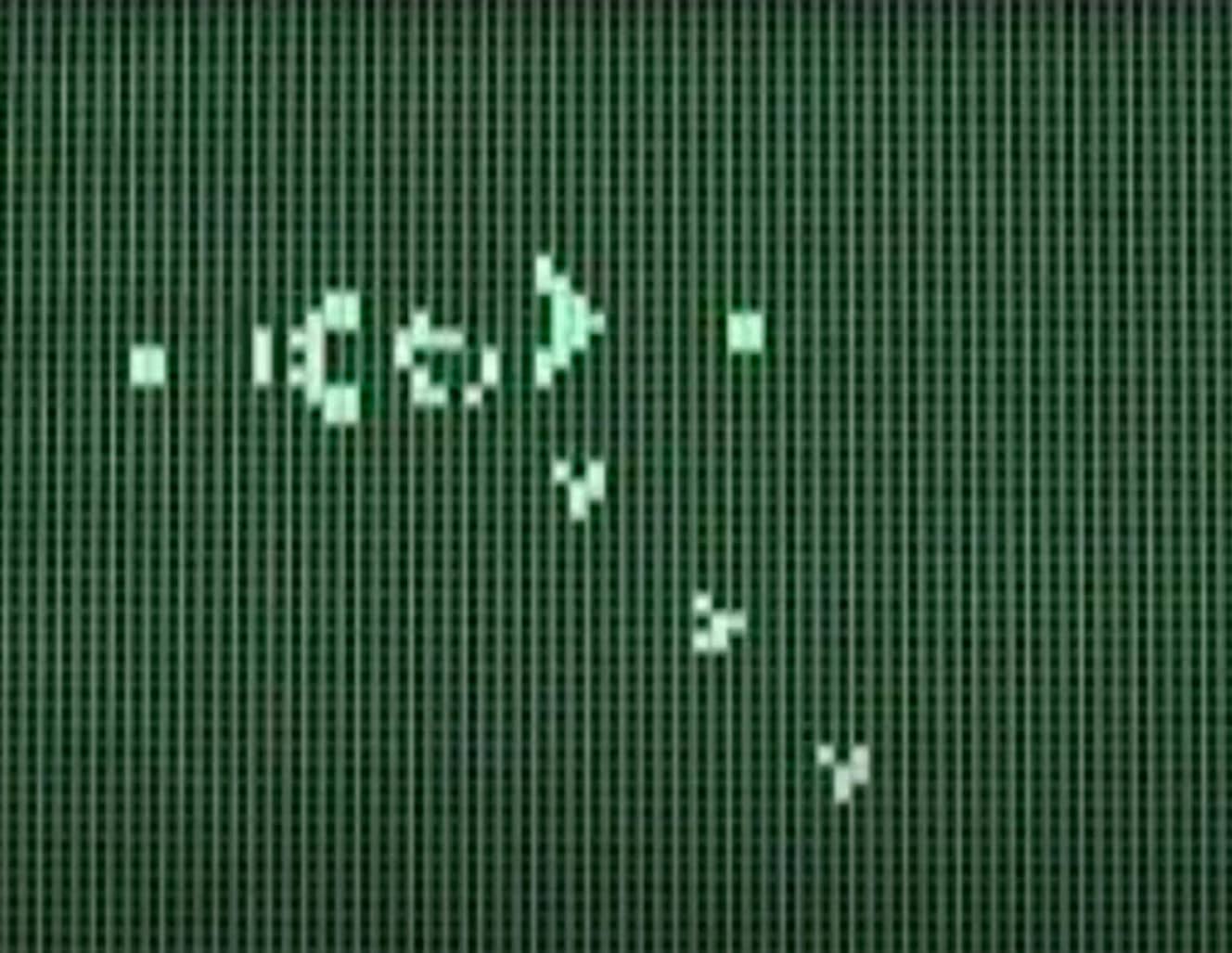
コンウェイは1970年に『LIFE』というゲームプログラムを発表した。それはフィールドに細胞状の生命体がドット(点)で描かれたもので、プログラムを起動すると、これらがアルゴリズムに従って増殖と消滅を繰り返し、生命の営みをシミュレーションしてみせる。今のゲームと比べたら非常に原始的なグラフィック表現だが、コンウェイが提示したプログラムは現在のAI(人工知能という概念)の始まりであり、コンピュータの中に生命を宿らせるという意味では、コンピュータゲームの原点のひとつ、とも言えるものだ。
現実では無理なことを疑似体験できるのがコンピュータゲームのいいところ。たとえば外科手術さえも!
コンピュータゲームには現実のシミュレーターとしての側面があり、これまで戦争、スポーツ、遊び、あるいは様々な職業がゲームの題材に選ばれてきた。そのうちのひとつに「医療」もある。『LIFE』が、その後のコンピュータゲームに与えた影響は計り知れないが、その直接的な影響下にあるのが「医療ゲーム」というジャンルだろう。
1982年に発表された『マイクローブ』(Synergistic Software)は、極小の潜水艦で患者の体内に入り込み、治療のため患部を目指すというゲームだ。潜水艦は異物とみなされ、白血球からの攻撃を受けるなどして、 治療は一筋縄ではいかない。

小型化して人間の体内に入り込むとは非常に大胆な発想だが、これには元ネタがある。1966年に公開され大ヒットしたSF映画 『ミクロの決死圏 』だ。脳に深刻なダメージを負った政府要人を救うため、開発されたばかりのミクロ化技術で潜水艇とドクターを縮小して患者の体内に送り込み、脳の内部から治療を試みるというものだ。映画としても心躍る設定だが、ゲームでは、それを実際に自分の手で操作できるのだからたまらない。
『ミクロの決死圏』の原題をそのままタイトルにした『ファンタスティックボヤージュ』(20th Century Fox Games)というゲームもある。発売元が20世紀フォックスなので映画の正式なゲーム化ではあるが、人体内で白血球やバクテリアなどを撃って進むシューティングゲームに仕上がっており、医療ゲームと呼ぶにはちょっと無理がある。

1983年には、日本でも『バイオアタック』(TAITO)というゲームが登場している。これは先の『ファンタスティックボヤージュ』をアーケード用に移植したもので、ゲームセンターで遊んでもらうなら、むしろシューティングゲームであることが都合が良かったに違いない。
まったくの素人でも外科医の仕事を体験できるのが、ゲームのいいところだ。『サージョン』(1986年、ISM)や『Life & Death』(1988年、The Software Toolworks)といったゲームでは、患者の腹部を切開して外科手術をすることができる。ただし、かなりリアルにシミュレーションされているため、遊び気分で取り組むと大変なことになる。ほんの些細なミスが患者を死に至らしめることになるのは、ゲームも現実も同じだ。


家庭に居ながらにして生命の神秘と深淵に触れることもできる
ここまではおもにパソコン用のゲームを取り上げてきたが、ファミコンが大ヒットして以降、ゲームは急速に一般家庭にも普及した。当然、家庭用のテレビゲームにも医療を題材にしたものが登場するようになる。
1999年にPlayStation 用として発売された『クリックメディック』は、これもまた『ミクロの決死圏』のように体内に入り込んで患部を目指すゲームだが、特徴的なのはその移動方法だ。インターネットのハイパーリンク構造を応用しており、体内の様子を描写したテキストの中から、 行き先や体内部位を示した単語(タグ)をクリックすることで、目的の場所へ移動する。『かまいたちの夜』などのテキストアドベンチャーの体内版、といったらわかりやすいだろうか。
めでたく患部にたどり着くことができたら、今度はそこに巣食っている病原体(ゲーム中では“バクルス”と呼ばれる)との対決だ。こちらの攻撃に対して増殖と消滅を繰り返すバクルスの動きは、まさにコンウェイの『LIFE』を思わせる。

ニンテンドーDS用では、『研修医 天堂独太』(2004年、Spike)や『超執刀カドゥケウス』(2005年、ATLUS)といったゲームがある。携帯ゲーム機というカジュアルなプラットフォームにふさわしく、どちらもキャラクターのネーミングやデザインがしっかりと設定され、ヒットに伴ってシリーズ化もされている。
ゲームと現実の境界が曖昧になってくる……?ウイルスを蔓延させる ゲームもあった!
2011年に登場して大きな話題を呼んだのが、スマホ用アプリの『Plague Inc -伝染病株式会社-』(Ndemic Creations LTD)だ。
これまで医療ゲームといえば病気の克服を目指すのが当たり前だったが、これはそのまったく逆で、プレイヤーは患者に感染させた病原体を全世界に蔓延させ、人類の歴史に幕を降ろすことが目的となる。もちろん、あくまでもゲームの中での架空の遊びではあるのだが、現実に致死性のあるウイルスが世界中に蔓延している今、振り返ってみると、そのあまりにも不謹慎な設定にはめまいがしてくる。

ちなみに、開発元のNdemic Creations LTDでは、新型コロナウイルス対策への財政支援として、「COVID-19連帯対応基金」へ合計25万ドルの寄付を行うと共に、今後のアップデートでは病気から世界を救うモードも搭載する予定だという。
……というわけで、このように医療や病気を題材にしたゲームをひと通り見てきて心から思うのは、世界を脅かしているコロナ禍が「ゲームだったらよかったのに!」ということだ。
しかし、残念ながらこれは現実だ。だからこそ世界中の医療従事者たちは、一刻も早く事態を収束させるために、今この瞬間も最前線で頑張ってくれている。そして、われわれ一般の人間も、感染の拡大を食い止めるため自粛生活に取り組んでいる。
家から出られないことは、思いのほかストレスがたまるものだ。それを解消するために、みんな様々に工夫を凝らして楽しんでいる。テレビゲームで遊ぶこともまた、そのひとつの方法だ。『あつまれどうぶつの森』もいいけれど、現実に集まるわけにはいかない今は、医療ゲームをチョイスしてみることで、医療関係者の苦労に想いを馳せてみるのもいいかもしれない──。
- 文:とみさわ昭仁
