40代で増える仕事ミス…原因は認知機能の低下?専門家の答え
認知症予防・未病のための「健脳カフェ」取材レポート
もしかして、“自分だけが気づく”『SCD(主観的認知機能低下)』という段階!?
光浦靖子の著書『50歳になりまして』(文藝春秋)の中に、レギュラーのラジオ番組を、曜日の勘違いによってうっかりトバしてしまったというエピソードがある。
実は自分も50歳近くになり、一時的にこれまでなかったようなミスを連発し、にわかに不安になっていただけに、かなりヒヤリとする話だった。
仕事相手の信頼を失いそうで言いにくいが、例えば……。
- ・原稿を早めに書き終えたのに、食事をしている間に送信を忘れる。
- ・取材の予定を1日間違える(前日だったから良かったが……)。
- ・締め切りを「〇日」とスマホに登録したが、時間を入力しておらず、夕方までのつもりが実は正午までだった……。
- ・早めに原稿をあげるために締め切りの1日前倒しでスマホに入力。それを忘れて大慌てで執筆し、「そういえばもう1日あるんだった……」。
元来のおっちょこちょいぶりに加え、自分のキャパ以上に仕事をしすぎているということなのか、単純に加齢による変化か、それとも認知機能に問題が?
不安になり、ネットで調べてみると、自分と同じく40代くらいから仕事のミスが増えたというつぶやきが多数見られた。気になるのは、心配なケースとそうでないケースの違いである。
そこで、取材に訪れたのが、今年4月東京・四谷にオープンした認知症予防・未病のための拠点「健脳カフェ」だ。
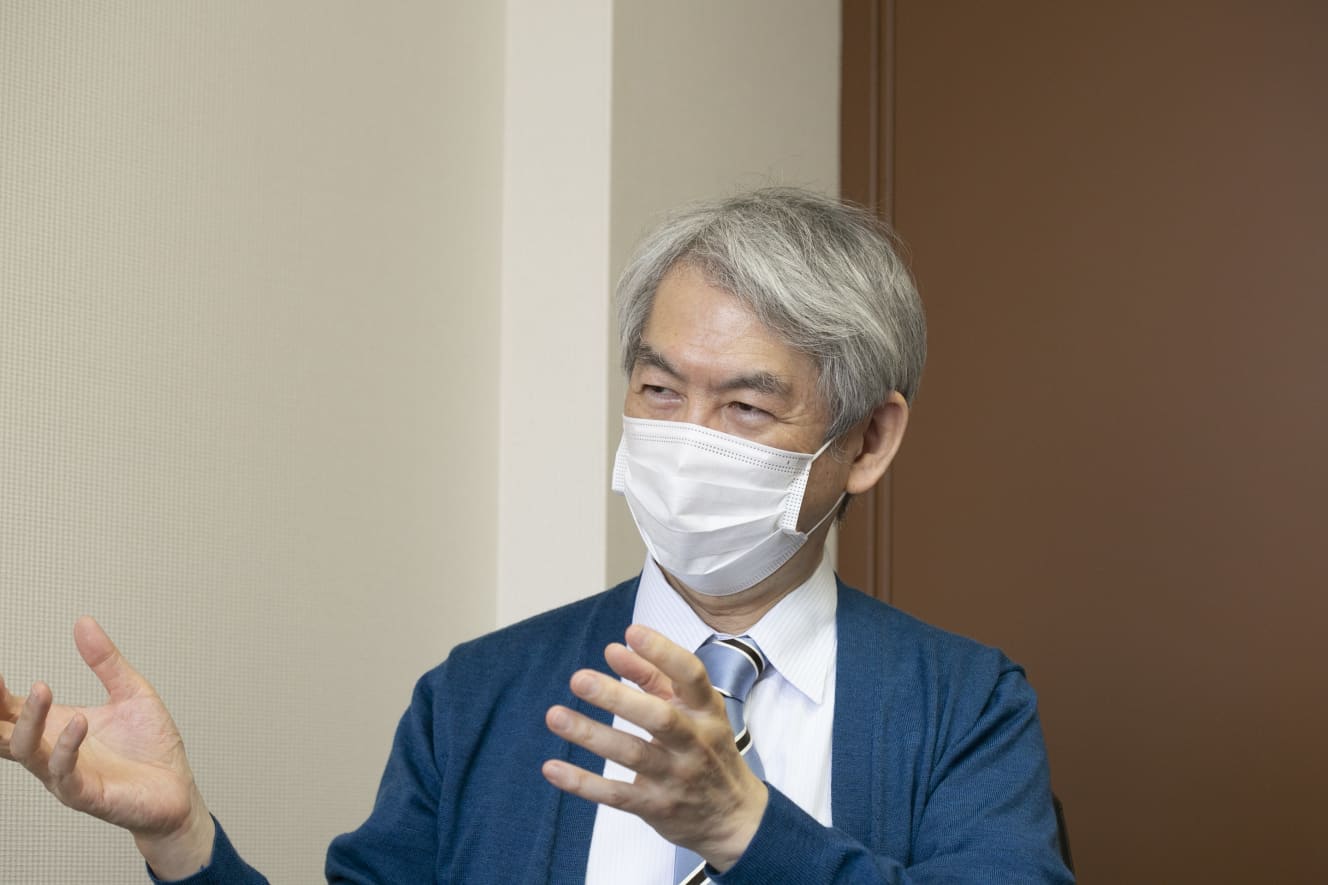

認知症の予防に一番有効なのは「運動」!? 最新の研究で判明
ここは体操や絵画教室、囲碁将棋などの体や頭を動かすレクリエーションを通じて認知症予防を目指す予防カフェで、この日の参加者は、軽度認知障害(MCI)と診断された人やその家族の計13名。30分程度の雑談後、参加者たちは、椅子に座ったままお腹を丸めたり、内ももに力を入れたり、膝を抱えて股関節を開いたりするストレッチを行っていた。
「最近の研究により、運動が認知症の予防に一番有効だというエビデンスがあるんですよ。
健康な筋肉と健康な神経細胞は、何もしないと衰えてしまう。一方、運動をすると、血流が良くなり、酸素が脳まで行き届くわけです。動物実験においても運動している動物と運動していない動物モデルを比較した場合、運動している方が、アミロイドβというたんぱく質が溜まりにくいということがわかっています。アルツハイマー病では、脳にアミロイドβというたんぱく質が蓄積し、それが引き金となり、タウというたんぱく質が蓄積します。タウはさらに神経細胞を障害し、脳の萎縮が起こると記憶障害に加え、日常生活に様々な症状が現れるのです」
そう話すのは「健脳カフェ」の監修者であり認知症予防の第一人者、順天堂大学名誉教授で「アルツクリニック東京」の新井平伊院長だ。
早速、自分のミスをあれこれ相談してみると、「原因は、今言った全部だよ」と新井医師が一刀両断。ええ……そんな……と、うなだれていると、こう補足する。
「性格もあるだろうし、キャパオーバーもあるだろうし、加齢も認知機能の衰えも、可能性は全部あるということ。ただし、それを記憶障害と考えちゃうからすぐ認知症という話になるんです。忘れると結果としてポカになるけど、記憶障害で抜けるんじゃなくて、注意とか集中の問題もあるわけで。例えば、他のことをやっているうちに忘れるというのは、注意が散漫になるという、サザエさんのような話で、それは記憶と違うわけですよ。
記憶というのは、いったん脳の中に入り込んで、そこから取り出すもので、脳の中に記憶として残らなきゃいけないわけだけど、残っていない話もあって。他のことをいろいろやっている場合に、パッパパッパと上書きされちゃうような記憶を『ワーキングメモリー』と言って、それは注意や集中の問題なんですよね」
そう聞いて、まず一安心。では、医療機関を受診する必要は特にないのだろうか、と問うと。
「一度は診てもらった方が良いでしょう。なぜかと言うと、今の考えは健康か病気か、黒と白に分けるような二分法だからです。
でも、実はこの間にはグレーゾーンがあるわけで、そうしたグレーゾーンには先ほど挙げたようなトラブルも前段階としてあるんです。
軽度認知障害(MCI)の場合、そういった物忘れが他人にも気づかれるレベルでありつつ、検査だと異常ナシとなる。さらに、その前に自分だけが気づいている『SCD(主観的認知機能低下)』という段階があるんです。
つまり、先ほど挙げた様々なトラブルは、このSCDに当たるもので、将来、アルツハイマー病になる可能性がある前段階でもあるわけです。もちろんそうじゃない場合もいっぱいある。だから、『検査を受けたほうが良いか』と聞かれたら、もちろん受けたほうが良い。
たとえば、自分で胃が痛いなと感じたとき、最初は自分しか気づかないけど、うずくまっていると、他人が気づくようになるでしょう。それが病気だとどんどん悪化し、場合によっては癌だったなんてこともある。
つまり、他人に『どうした? 胃が痛いのか?』と言われるのがMCIで、自分だけで痛みを感じているのがSCDで。気になるなら、医療機関を受診したほうが良いわけですよ」

認知症の七割を占める「アルツハイマー病」は、発症の20~25年前から始まる
では、40~50代で、仕事のミスが出てくるのは、そうしたグレーゾーン、SCDに当たる場合が多いということなのだろうか。
「そうです。ただ、40~50代は、社会的にいろんな責任を負いますよね。会社でも役職になったり、仕事が20~30代に比べて量が増えたり、結婚していてもしていなくても、人間関係もどんどん複雑になってくるし、住宅ローンを抱えていたりする。ライフイベントやライフサイクルを考えると、40~50代は20~30代に比べて、様々な要素が積み重なってくる、一つの危険な年齢なんですよ」
もちろん体と脳の老化の影響も大きい。
「20~30代のうちは無理しても体が元気なので、リカバーできますが、40~50代になると体の老化と脳の老化との両方が始まり、無理がきかなくなってくるというのもある。
もちろん処理能力もどうしても衰えてくるわけですが、その一方で処理しなくちゃいけない事は増えてくるので、オーバーフローになり、注意が散漫になる。
また、若い頃は前頭葉機能の働きが良く、普通に同時処理ができていたことが、前頭葉機能の衰えによって、だんだん出来なくなる。また、若い頃は徹夜をしても寝不足しても大丈夫だったのが、疲れが溜まるようになったり、深酒した後に前よりもお酒が脳への影響が出たり。そういった悪循環の始まりが40~50代であり、リスクそのものなんです」
つまり、こうしたミスが続出する時期というのは、仕事のやり方や生活のペースを見直し、ギアチェンジすべき時に来ているということだ。
「それに、40~50代でうまくギアチェンジができるかできないかによって、後の60~70代の結果が違ってくる。結果とは、つまり、10歳以上老化が早くなるということ。40~50代から寝不足になるわ、運動不足になるわ、おまけに生活習慣病になるなどの危険因子が増えてきて、それらを解決しないままに、仕事もオーバーフロー状態をずっと続けていくと、脳の萎縮が進む可能性があるということです」
ちなみに、「WHO認知症予防ガイドライン」では、以下の12の項目に分け、それぞれについて一般的に「認知症予防に良い」と言われる事柄のエビデンスを検証し、推奨レベルを紹介している。
- 身体活動(強)
- 禁煙(強)
- 栄養的介入(強)
- アルコールの使用障害への介入(条件による)
- 認知的介入(条件による)
- 社会活動(支援されるべき)
- 体重管理(条件による)
- 高血圧の管理(条件による)
- 糖尿病の管理(条件による)
- 脂質異常症の管理(条件による)
- うつ病への対応(条件による)
- 難聴の管理(エビデンスが不十分)
最後に、新井医師は40~50代に向け、こんなメッセージをくれた。
「アルツハイマー病は認知症の七割を占めています。これは発症の20年前、25年前から始まる病気で、例えば70歳で発症する場合、病気が始まっているのは45歳~50歳ということですよ。
つまり、40~50代から脳の中の変化はどんどん始まってしまっていて、アミロイドβがどんどん蓄積し、神経細胞にダメージを与えているわけです。
そう言った意味で、実は40代というのは70歳で始まるアルツハイマー病にとっては非常に大切な時期なんですよ。特にSCDの段階で気づくことができれば、生活改善で発症や進行を抑えることも可能です。変化を見逃さないよう、定期的にチェックし、気になる症状がある人は医療機関を受診しましょう」


新井 平伊(あらい へいい) アルツクリニック東京院長・順天堂大学名誉教授。順天堂大学医学部附属順天堂医院・メンタルクリニックで長年主任教授を務め、順天堂大学退官後の2019年より精神科・内科のクリニック、アルツクリニック東京を開院。著書に、長年の認知症の外来で培われた経験と最新の研究成果をもとにした『脳寿命を延ばす 認知症にならない18の方法』(文春新書刊)などがある。
- 取材・文:田幸和歌子
- 撮影:安部まゆみ
